本家白石焼
起源は鍋島藩祖勝茂公の時代によるもので、我が家の陶祖藤崎百十は、文化三年白石藩主鍋島直高公の招きにより、西松浦郡大川内より来て、藩公御用窯となり、磁器走波焼を作る。 以来、ロクロと炎一筋に伝統を守って現在に至る。
伝統
有田が西目の皿山、白石が東目の皿山と称されて以来、古い伝統の中に新しい技術を競って、親しみのある陶器作りをしています。 百十窯は、由来と伝統を守り近代的溢れる光彩と、滋味を発揮し、人々の暮らしの中にとけこむ陶器作りに専念するかくごです。

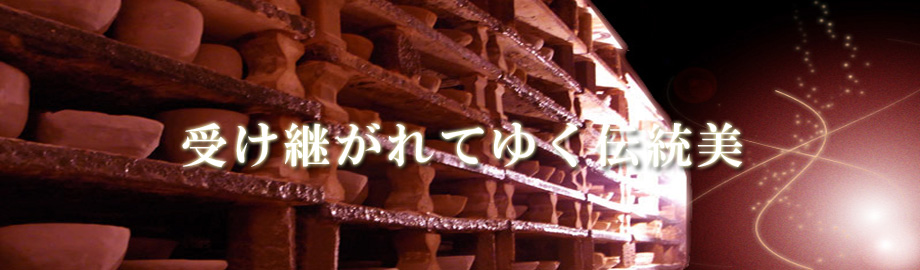

金右衛門が焼く陶器は隣国の久留米藩などで評判を生んだ。
その後、寛政12年、鍋島藩お抱えの陶工、藤崎百十が天草の陶石を使った磁器を焼き始めた。
更にその数年後、文化3年には佐賀鍋島藩の分家である白石鍋島家が御用窯として知られていた伊万里の大川内山から陶工を招き、本格的な磁器産地とした。
起源は鍋島藩祖勝茂公の時代によるもので、我が家の陶祖藤崎百十は、文化三年白石藩主鍋島直高公の招きにより、西松浦郡大川内より来て、藩公御用窯となり、磁器走波焼を作る。 以来、ロクロと炎一筋に伝統を守って現在に至る。
有田が西目の皿山、白石が東目の皿山と称されて以来、古い伝統の中に新しい技術を競って、親しみのある陶器作りをしています。 百十窯は、由来と伝統を守り近代的溢れる光彩と、滋味を発揮し、人々の暮らしの中にとけこむ陶器作りに専念するかくごです。